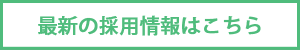認知症とどう付き合うのか~9月25日開催花カフェレポート
第17回「みなさんのしゃべり場 花カフェ」が9月25日、よみうりランド花ハウスのデイサービス・ルームで、「認知症とどう付き合うのか~高齢者の薬物療法とそのリスク~」をテーマに開かれました。講師は、高齢者医療や薬物療法の現状を鋭く分析、著作活動などで問題点に警鐘を鳴らしているフリーライターの東田勉さんで、認知症の方やそのご家族、地域住民の皆さんなど46人が参加しました。東田さんは、年齢によって変化する認知症の診断の難しさや、認知症と精神病の薬の服用の問題点などを端的に説明し、認知症高齢者を介護する人々に対して、各地で活動する家族会に気軽に相談するよう呼びかけたほか、的確な診断や治療法を身につけた専門医探しの重要性を訴えました。
以下、概要をレポートします。
◇
「厚労省の認知症高齢者推計値への疑問」:厚労省が出している公式の認知症高齢者の推計値(2012年462万人→2025年700万人)は、自著「認知症の『真実』」で「これは推計値ではなく目標値だ」と皮肉を込めて指摘したように、こんなに増えるはずはないと思われる。共同通信社が2016年3月に配信した米国の疫学調査結果によれば、米国では認知症患者が10年ごとに20%ずつ減っている。米国では認知症患者は減る傾向にあるのに対し、日本では増えており、どちらかが間違っているのではないか。
「認知症という病気はない」:認知症という病名は2004年、それまでの痴呆症に変わる名称として作られた。アルツハイマー病、脳血管疾患などで日常生活に支障が出る程度にまで記憶機能やその他の認知機能が低下した状態、というのがその定義だ。しかし、一口に言ってがんという病気がないのと同様に、認知症という病気もない。がんでは、どこの場所のがんかが問題になるように、認知症では、記憶障害などが進むアルツハイマー型、パーキンソン症状やうつ状態などが出るレビー小体型、反社会的行動が出やすくなる前頭側頭型(ピック病)、夜間のせん妄やうつ状態などが出る脳血管性、と4つに大きく分けられ、型によって薬の使い方も違ってくる。
「誤診や治療の難しさの理由」:認知症は、年齢とともに異なる型の認知症との合併や移行がとても多い。アルツハイマー型や脳血管性の認知症でも、80歳を超えて年齢が進むにつれて、レビー小体型やピック病型に移行したり、合併症状が表れたりする。このため、正確な診断や治療が難しい。さらに、認知症の症状は、記憶障害や判断力低下、性格変化などの中核症状と、徘徊、暴力、妄想、うつ状態などの周辺症状(BPSD)との二重構造になっており、BPSDには陽性と陰性があることも治療を難しくしている。
「薬剤使用の問題点」:抗認知症薬にはアリセプトなど4種類があるが、いずれも認知症の中核症状の進行を一時的に遅らせる効果しかない。BPSDには、興奮を抑えるなどのために精神安定剤、抗うつ剤などの向精神薬を使うが、寝たきりになるなどの副作用もある。抗認知症薬には用量規定があり、例えば、アリセプトは日量3㎎から飲みはじめて5㎎、10㎎と段階的に増量することになっているが、5㎎を飲んだ人の20%~30%が興奮して怒りやすくなる「易怒」の症状が出るという臨床データがある。抗認知症薬と向精神薬を併用すると、アクセルとブレーキを同時に踏み込んだような治療になってしまう。また、3㎎でも10㎎でも状態の変わらない人もいる。抗認知症薬はいったん飲み始めると、増やすことはできるが減らすことができず、1人1人にふさわしい服用ができないことが問題だ。
「認知症とどう付き合うのか」:政府は2015年から認知症国家戦略(新オレンジプラン)を進めていて、全国360か所の病院を認知症疾患医療センターとして指定しているが、その6~7割は精神科病院で、脳の病気は精神科へというのが方針だ。しかし、欧米では、認知症の人は精神科に行かない。認知症は脳の病気と心の病気が合併した病気だと捉えられるが、日常生活できちんと援助すれば、問題行動や心理症状は減るという。認知症の患者に対しては、むやみに精神科を受診せず、コウノメソッド(名古屋フォレストクリニックの河野和彦院長が提唱する認知症医療)実践医(全国に350人)など経験豊かな医師を探して、的確な診断や治療を受けさせるとともに、薬剤に頼らずBPSDが出ないようにする適切な援助と組み合わせていくなどのやり方で対処すべきだろう。