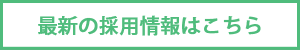人と人がつながる喜び~マンモス町会の活動と魅力とは【花ハウスの人々27】

川崎市多摩区にある菅町会は、約8000世帯の会員を抱える全国でも最大規模のマンモス町内会です。3階建ての専用の会館を構え、職員2名が常駐。防災に取り組む自主防災組織が18あり、大運動会や子どもフェスといった行事や珠算・英語・書道教室も開講しています。副会長で、地域密着型特養「花ハウスすみれ館」の運営推進委員でもある真鍋るり子さんに、町会の活動と魅力を聞きました。
菅町会の発足は1953年、それまで自治活動を担ってきた菅公民館の名称を引き継ぐ形で出発しました。以来、「できる範囲のボランティア」を合言葉に、地域のみんなが安心して快適な生活ができる街づくりに70年以上にわたって取り組んできました。
防犯灯やカメラの設置、防犯パトロールといった安全なまちづくりや、災害発生時の避難所開設といった防災活動、献血や救命講習、健康づくりといった活動など、活動は多岐にわたります。女性部や熟年部、体育部といった13の部と、補導や防災、救護といった7つの委員会で構成されています。骨盤ストレッチや茶道、ハワイアンキルトの講座もあります。

3階建ての町会専用会館
真鍋さんが2003年に菅地区にきたとき、周りは知り合いない人ばかりでした。その後、町会活動を通してひとりずつ、いろんな人と知り合いました。「それが今の自分の財産になっています」。町会活動の最大の魅力は人と人とがつながること、といいます。17年に副会長にと推されて引き受けたのは、断る理由がなかったからでした。母を見送り、仕事もしておらず、「何かお役に立てるのなら」という気持ちでした。現在は副会長として教養部や厚生部を担当しています。
町会が特に力を入れているのが防災活動で、平時から防災に関する知識の普及や危険な場所、避難経路の確認、医薬品や救出機材、炊き出しに必要な備蓄や管理につとめます。真鍋さんも南菅中学校避難所運営委員長として活動しています。
過去の大災害では、住民同士の結びつきの強い地域ほど、住民の安否確認や行方不明者の捜索、避難所の運営が円滑に行われてきました。「あそこにおばあさんがいたはずと知っていれば、命を助けられるかもしれない。知っている人がいるというのは、いざというときに力になります」と、真鍋さんは「顔見知りの力は大きい」を強調します。一世帯月150円の町会費を一軒一軒集めて回る町会の仕組みも、「人と人とがつながるには、まずどんな人か知ることから始まる」という考えからです。
地域のお年寄りとのかかわりでいえば、毎年11月3日に数百人規模の敬老会を開き、60歳以上対象のバス旅行は大盛況、ゲートボール大会、社会福祉協議会とタイアップしての食事会といった活動を展開しています。年齢を重ねるごとに孤立しがちなお年寄りを行事で地域の人たちにつなぐ役割を果たしています。

ただ、全国のほかの町内会と同じく、菅町会の組織率も年々低下を続けています。このためSNSを活用した広報活動に力を入れ、スマホで見やすいホームページも運用しています。町会事務のIT化にも取り組んでいます。
真鍋さんも各世帯を回り、町会活動への参加を呼び掛けています。「町会への加入を呼びかけると、『メリットは何ですか』と聞かれることが多いんです。でも、直接的なメリットはありません。地域の人を知る、つながりを持つことが長く暮らす上でどれだけ大切かを理解してもらえるかです」と教えてくれました。老人介護施設も、地域の一員としてどうあるべきか、考えていかなければいけません。(剛)