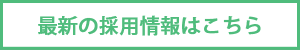20代半ばで人生の転機~介護のプロを目指し、楽しみながら進化していく【花ハウスの人々21】【花ハウス20周年】

5階主任のMさん(39)は20代半ばで副主任に任命されました。今から15年前のことです。派遣職員として働き始めてから、わずか半年後のこと、副主任になるのは普通、30歳を過ぎてからなので、抜擢でした。
「あなたならできる。年齢は関係ないから」。そう先輩主任から声をかけられたそうです。「何で自分なんだろう」「務まるだろうか」。悩んだ末、副主任を引き受けました。「人生のいい勉強だと思って受けてみなさい」という家族の後押しもありました。しばらくすると、その先輩が看護師になるために退職し、異例の若さで主任となりました。学生時代、部活動でキャプテンを任されることが多く、どんな人ともコミュニケーションをとれる性格が評価されたのかもしれません。
まわりは自分より年上や長く勤めている人ばかりでした。職員の不満が容赦なくぶつけられました。突き上げは厳しく、やっかみからか、よそよそしい態度をとる人がいました。どうしたらみんなの信頼を得られるだろうかと、考えない日はありませんでした。だれもが役職者になると部下との関係に悩みますが、苦しい日々でした。もともと強気な性格でしたが、人間不信に陥ったこともあったそうです。でも、あの頃があったから、今の自分があるほど、自分を成長させてくれた、人生の転機でした。

「寄り添う派」と「笑わせる派」
スポーツは得意ですが、勉強は苦手というMさんが介護の仕事を知ったのは、中学生のときです。ボランティアで近所の老人福祉施設に出向き、お年寄りと言葉を交わすと、「同世代よりも自分の話を聞いてくれるし、すぐに笑ってくれる。あっ、いいかも」と思いました。
小さいころから、おばあちゃん子。自分の話を聞いて、お年寄りがゲラゲラ笑ってくれるのを見ると、自分自身の心までもが豊かになるように感じるそうです。ほかの職員が利用者様と笑顔で話しているのを見ると、自分も楽しくなってきます。
Mさんによると、介護職には二つのタイプがいます。利用者様の話にじっと耳を傾ける「寄り添う派」と、利用者様にどうしたら笑ってもらえるかをいつも考える「笑わせる派」です。同じフロアの何人かの女性職員は寄り添う派ですが、Mさんを含む男性職員の何人かは笑わせる派。アンテナをはり、利用者様が何に関心があるかをキャッチします。その話題を調べてみたり、自分なりの声掛けを考えたりして、アプローチすると、うまくいくことが多いそうです。
介護の技術は、先輩の背中を見て学んできました。勉強が苦手だったこともあって、本を読むよりも、直観や感覚を働かせて現場で必要なことを覚えてきたといいます。ただ、最近は未経験で施設に入職してくる人も多いため、わかりやすく伝える難しさも感じています。「自分の背中で見せても伝わらないので、頭悪いなりにたとえ話で伝えたりしています」
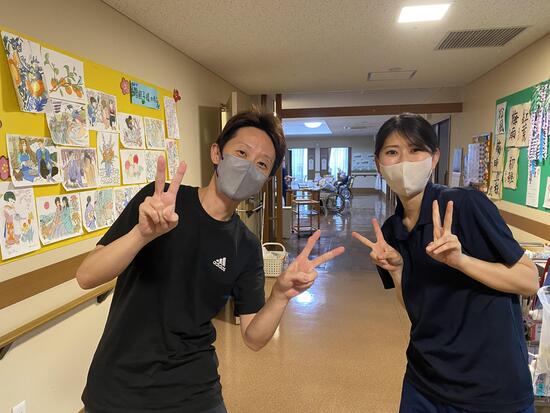
どの世界にもプロがいる
デスクワークより体を動かす方が好きだったので、介護の仕事にはすんなり入れました。18年間働いた36歳のとき、ほかの仕事もやってみたいと一時、転職を考えましたが、最終的に次の理由から介護を続けることを決断します。
「どの世界にもプロフェッショナルがいる。仕事を続けていくうえでモチベーションとなるのは自分もプロになりたいということ。そして、自分がプロになれる可能性が最も高いのは介護職」
自分はまだプロとはまだ言えないかもしれないが、やるんだったらプライドを持って仕事をしていきたい。そう悟ったそうです。では、プロとそうでない人の境界線はどこにあるのか。ヒントは意識の持ち方にあると、Mさんは考えています。
車を運転していて交通法規を守っていても事故を起こしてしまうことはあります。介護の現場でもルールを守っていたからといって、事故を起こさないとは限りません。重要なのは意識。常に根拠や危険性を考えながら介護する、漫然とやらない、作業的にならない、そうした気持ちの持ち方で防げる事故は多いそうです。
「介護ならできると思ってきました」。新しく施設に入ってきた人がそう口にするのを聞くと、がっかりします。「介護は、そんなに甘い世界じゃない。介護で大切なのは利用者様の立場に立つこと、自分本位ではいけない。人の心をよみとって事前に動いたりできるのは、簡単ではないと世の中の人にはわかってほしい」
インタビューの最後に某テレビ番組と同じく、「プロフェッショナルとは」と尋ねてみました。「この業界にプロというライセンスはないですし、現状プロと言える自信もありません。でも、現役で働かせていただいている以上、それを追求して楽しみながら進化していきたいと思っています」。Mさんは、そんな言葉で応じてくれました。(剛)