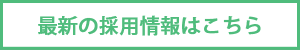「昔の記憶に入れていただき、『はじめまして』の壁を越えました」「その発想は天才です」【花ハウスの人々22】【花ハウス20周年対談3】

よみうりランド花ハウスの20周年を記念する対談の第3弾は、親子ほど年の違う3階主任のKさん(60)と5階のMさん(24)です。「できるかぎり利用者様の生活時間に合わせたい」「コミュニケーションとはすなわち安心のこと」。大学を卒業して介護職3年目のMさんは、介護職として20年働いてきたKさんの言葉に熱心に耳を傾け、メモを取っていました。
利用者本位を目指す
Kさんが介護職として働き始めたのは、花ハウスがオープンした約半年後のことです。軽貨物自動車を使って荷物を届ける赤帽の仕事をしていましたが、駐車違反で免許停止となり、仕事ができなくなった時間でホームヘルパー2級の資格をとりました。平日は赤帽、週末だけ花ハウスで介護のパート勤務という日々を1年送りましたが、「介護の仕事一本でいこう」と花ハウスでフルタイムの仕事に就いたそうです。
「仕事を始めてしばらくは色々覚えて面白くなったけれど、利用者様のケアを時間通りにこなすことばかり考えていました。今思えば、全然いいケアができていませんでした。大事なのは利用者様にいいケアを提供できているかどうか、なんですよね」
当時を振り返ってKさんが言うと、Mさんが驚いた表情を浮かべました。「僕はまさにいま、その段階、グサッと刺さりました。作業的になっているとは思わないけれど、利用者さま第一で動くべきですよね」
入所者様の生活は、どうしても介護職員の勤務スケジュールに左右されます。基本、早番の職員が出てきてから朝食ですし、就寝時間は遅番の職員が帰る前です。でも、そのスケジュールに合わせられない利用者様もいます。朝起きたくない人にはそのまま寝ていてもらう、朝食を食べられなかった人に差し入れのお菓子を後で食べてもらう。そんな風に、「できる範囲で寄り添う。合わせられることは合わせてあげる」。利用者本位を目指すのが花ハウスだと、Kさんは考えます。

介護現場での巻き込み力
Mさんは聞きたいことがあったようです。「フロアのレクリエーションを企画する行事委員をしていますが、ほかの職員と熱量に差がある場合、どうしたらいいんでしょうか」。父の日に新茶を味わったり、カードを手づくりしたりと、様々なアイデアを形にしていますが、職員の参加意識に濃淡が出てしまうことがあります。介護の仕事はチームワークです。周りの職員をどう巻き込んでいくかが問われます。
そこでKさんが知恵を授けます。ひとつは役職者に協力を求めること。役職者に「●●さんに協力してもらいたいと思っているんですけど......」と言えば、一緒に職員に声掛けしてもらえることもあります。
二番目は名付けて相談作戦。「何かいい知恵はないですか」と相談し、他の職員が「こんなやり方があるんじゃない」と言ったら、すかさず「じゃあ、それお願いしてもいいですか」と言います。Kさんが強調したのは目的や役割をきちんと説明すること。例えばスイカ割であれば季節を感じてもらうこと。Kさんの言葉にMさんはうなずき、メモ帳に何やら書き込んでいました。
 10年あまり前に撮影した写真。左がKさん
10年あまり前に撮影した写真。左がKさん
3人の指導役から異なる角度で教わった
Mさんが印象に残っているのが、1年目に先輩から受けた指導です。担ったのは、プリセプターという新卒者の先生役となる職員、所属するユニットのまとめ役である主任、別のベテラン職員の3人。そばにいることの多いプリセプターは少し厳しめ、主任は少し離れた場所から見守り困ったときに手を差し伸べてくれました。知識が豊富なベテラン職員は、利用者様にベッドから車いすなどに移っていただく際の移乗介助や、呼吸器系に疾患のある方との接し方など、技術的なことを教えてくれました。
「異なるタイプの指導を受けたことで、いろんな見方に気づきました。利用者さんの行動ひとつひとつに意味があり、そこからケアを考える。ケアには根拠と意味があるという、考えの根本を作ってもらう指導でした。後になって、あえて別な角度から3人が指導していたと聞きました」。今年4月には新人職員が入ってきて、Mさんも先輩になりました。自分が教わったように後輩に教えられるようになるのが目標です。
「新人には、業務的なことより、まずはコミュニケーションの大切さを学んでほしい」とMさんが言うと、Kさんは「いいですねー」と目を細めました。「コミュニケーションの基本は仲良くなること。知らない職員から話をかけられるより、『この人とこんな話をしたな』という記憶のある職員から声をかけられる方が、利用者様も安心します。コミュニケーションはすなわち安心です」

「この仕事を選んで正解だった」
40歳になってから介護の世界に入ったKさんには、Mさんに聞いてみたいことがありました。「僕が若いころには、介護という仕事は選択肢になかった。どういうきっかけで介護の仕事に就いたの?」
大学で経営学を学んだMさんは、就職活動でコンサルタント会社なども受けたそうですが、自分がスーツを着て働くことに何か違和感があったといいます。小さい頃からおばあちゃんと接することが多かったため、お年寄りの接する仕事が向いているのではないかと考えました。「やりやすいことをやってみようと思いました。今はこの仕事を選んで正解だったと自信をもっていえます」
認知症の方と接するときの工夫は試行錯誤を重ねています。毎日のようにあっていても、会うたびに「はじめまして」となってしまう方もいます。関西出身の女性の方は、会うたびに昔食べた中華料理屋さんの話をされます。その方があるとき、「あんた、あの店で働いていたよな」とMさんに声をかけてくれました。否定できずにいたら、いつしか中華料理店で働いていたお兄ちゃんとして、女性の記憶にインプットされました。会うたびに「うまかったよね、あれ。あんた、あそこで働いていたな」と声をかけられるようになり、「はじめまして」の壁を越えました。
「今の記憶に入り込めないので、昔の記憶に入りこむような不思議な感覚でした。自分は24歳なので、年齢的にはあり得ない話なんですが......」というMさんに、Kさんは「その発想は天才です。認知症の方は、記憶はなくても感じている。『はじめまして』と言っても、初めてじゃないということには気づいているんです」と言葉を返しました。
2人はフロアが違い、ふだんあまり話す機会がありません。今回の対談で、お互いに刺激を受けたようでした。日々の介護を通じて培ったそれぞれの思いが共鳴し、花ハウスの介護がつくられていきます。(剛)